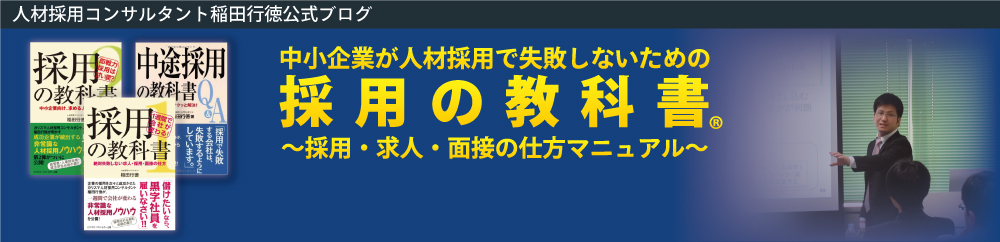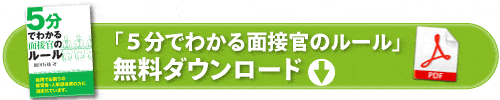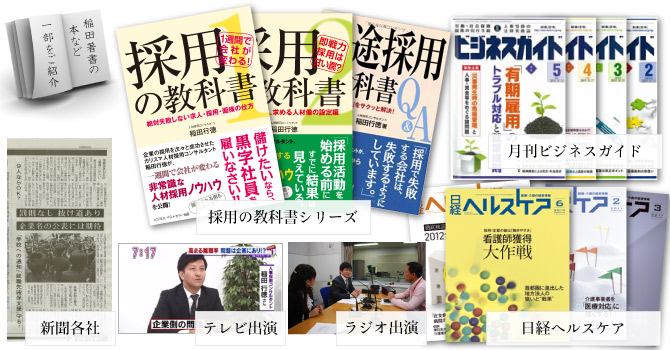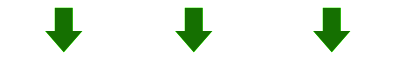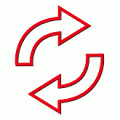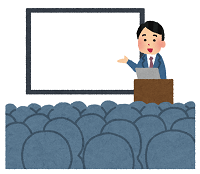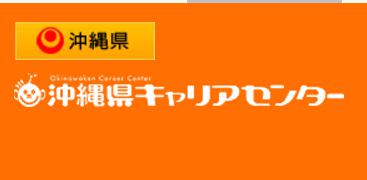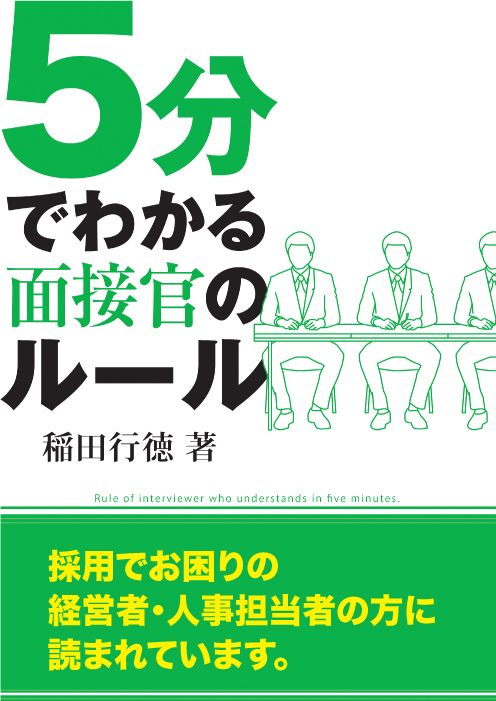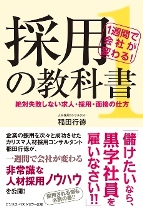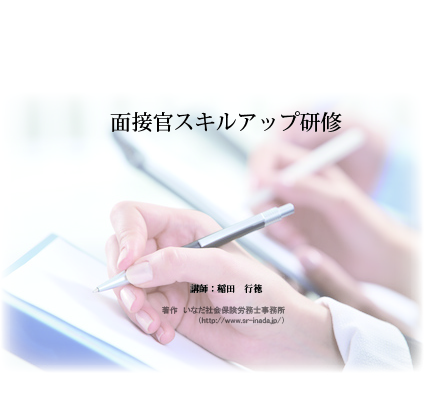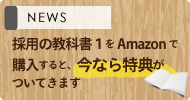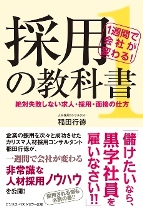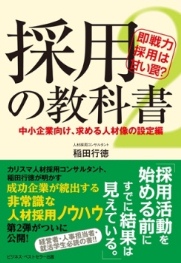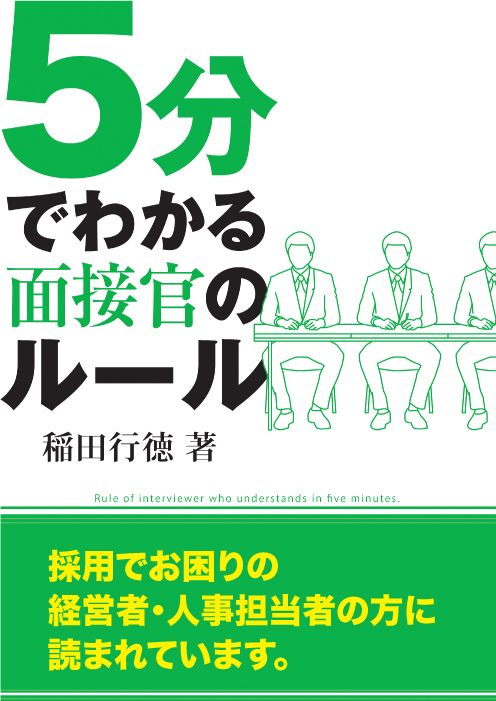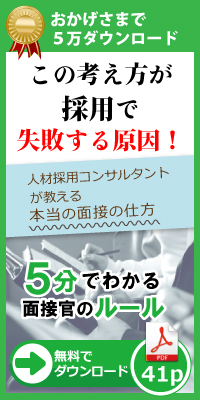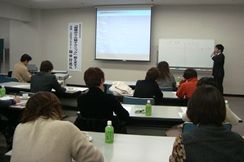企業も芸能人も一般人もTwitterをしましょう
最終更新日:2022/02/15
 Twitter(ついったー)はご存知ですか?
Twitter(ついったー)はご存知ですか?Yahooニュースや色々なメディアで最近注目されてきていますが、私が始めたのは数か月前でした。
まずはテストの意味をこめて試していたのですが、うまく使うことでそれなりに使えることが分かりましたのでご紹介します。
Twitterとは?
分かりやすい記事がありましたのでそれを引用します。あなたは「ひと言新聞」を発行しています。
購読希望者全員に自動的に届けられる新聞ですが、たまにあなたに「お手紙」をくれる人がいて、その人には個別に「特別お返事号」を発行します。
その人だけに届けるものなので、封筒には宛先を書かなければなりません。
それが、「@名前 」 です。名前に@をつけると宛先になるんです。
でも、その人に書いたお返事を他の人にも読んでもらいたい場合は、全員に届ける方法もあります。それが、.(ピリオド)のついた@です。
こうすると購読者全員が読めるお手紙になります。
もちろん@がついているので、最初に手紙をくれた人は「ああ、これはみんなが見てるけど自分へのお返事なんだな」と知ることが出来ます。
たまに、いただいたお手紙の内容や、他の人からの新聞があまりに素晴らしくてみんなにも知ってもらいたい場合は、新聞のコピーを配ることも出来ます。
それが RTのついた新聞です。
これは元の文章をコピーしたものですが、その中には書いた人の名前(@がついてますね?)が含まれるので、コピー新聞を読んだ人も、元の文章を書いた人が誰なのかを知ることが出来ます。
詳しくは☞パソコンが苦手な人へ~Twitterの仕組み~
簡単に言うとTwitterとは、「つぶやき。ひと言ブログ。ひと言新聞」です。
あまり難しく考える必要はありません。とりあえず始めてみたでOKです。
私のTwitterはこちら
(ここからTwitterを始められます)
https://twitter.com/saiyouinada
企業がTwitter使うなら
社長はブログを書きなさいでも書きましたが、メールが打てるのにブログをしない中小企業の社長はちょっとおかしいんじゃないかと思います。ほぼ無料で会社の宣伝ができるのにその手間をおしんで、レベルの低い広告代理店に高い金を払って広告を出し続ける。
商品はターゲットに知られてはじめて売れる。
だから知らせるための媒体を企業自らが持つことは長期的な経営戦略からも非常に意味があるんですが、、、
まあそんな感じでTwitterも使えます。
何ヶ月か様子を見ていましたが、企業でも使えそうです。
自社に興味がある見込み客を集めておけば
「新しいサービスを始めることになりそうです。
その名も●●●。これすごいですよ。詳細はこちらURL」
とつぶやくことで広告費用0円で広めることもできます。
またブログをされている人は
「●●についてブログに書いてみました。
これを知らないと人生損します。URL」
でブログへの誘導もできます。
当然、採用活動でも使えます。
自社に興味がある応募者を集めておけば、
「●月×日に会社説明会をすることになりました。
詳細はこちら URL」
とつぶやくことで、説明会の席を埋めることができます。
また新卒採用の場合など
「現在、内定承諾者が8名です。残り2名で新卒採用活動が終わります。
応募する場合はお急ぎください」
など最新の情報を一言で発信することができます。
ついたーにはメッセージ機能があるから応募者からの質問にも簡単にこたえることができる。
リスクは0です。
こういうのはやるかやらないか。ただそれだけ。
ブログを始めるのはちょっと大変そうだなと思っていたり、ブログの補助として使えそうと思われたのなら試してください。
何も減るものはありませんから。
ついったーへの登録はこちらからできます。
(私のついったー画面。ここから誰でも1分で登録可能)
https://twitter.com/saiyouinada
登録後は携帯を使って投稿するといいですよ。
※モバツイッターと言います。
Twitter関連のおすすめソフト(少しパソコン詳しい人向け)
TwitterをFirefoxに取り込み、ポップアップで教えてくれる。いちいち、Twitterを見に行く必要はない
Twitterのクライアントソフト。これ便利ですね。こちらもTwitterにいかなくても全部操作できますし、他の人の投稿を自動的に整理することができます。(読まないor読む分類を作ったり・・)Newtype税理士の井上先生が教えてくださいました。井上先生ありがとうございますm(_ _)m
追伸
私はたまにTwitter上でノウハウを出しています。
注意
Twitterを使ったスパム(迷惑行為)はやめましょう。